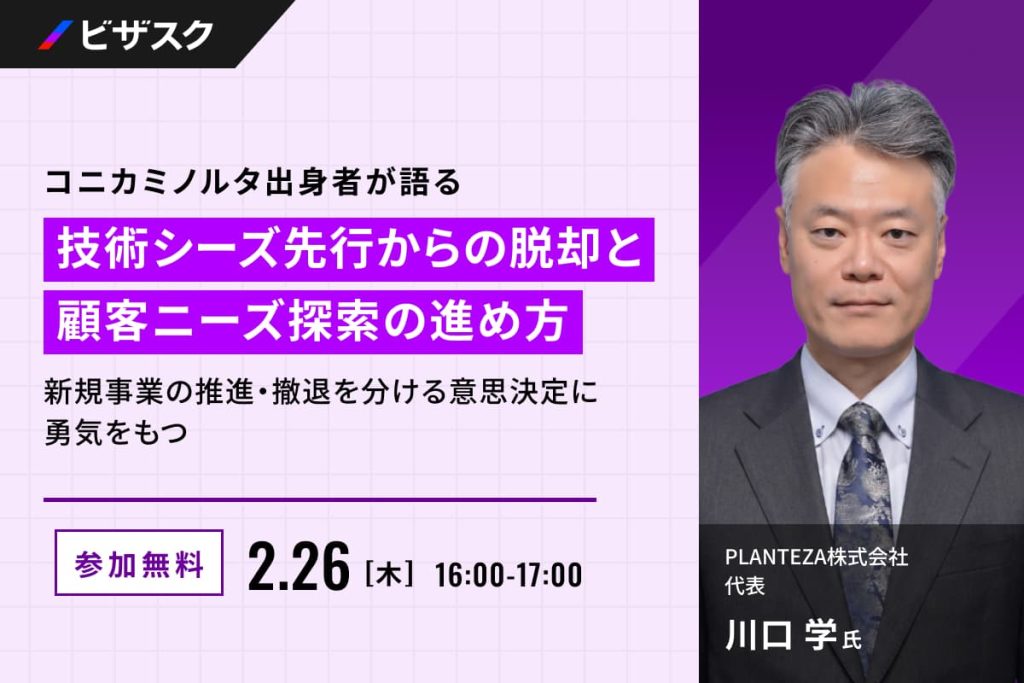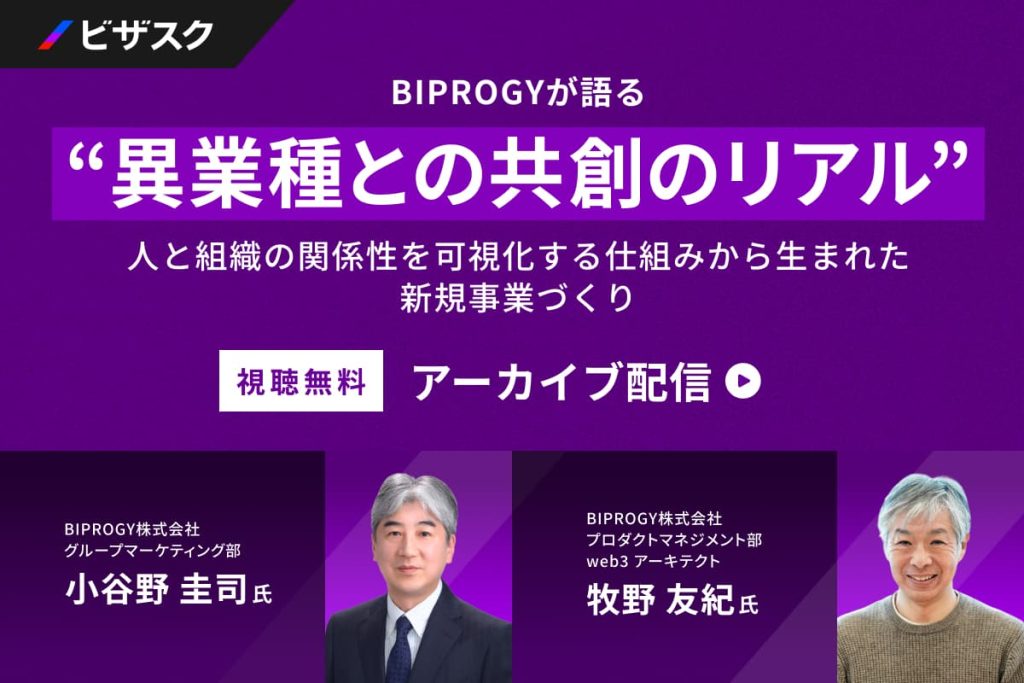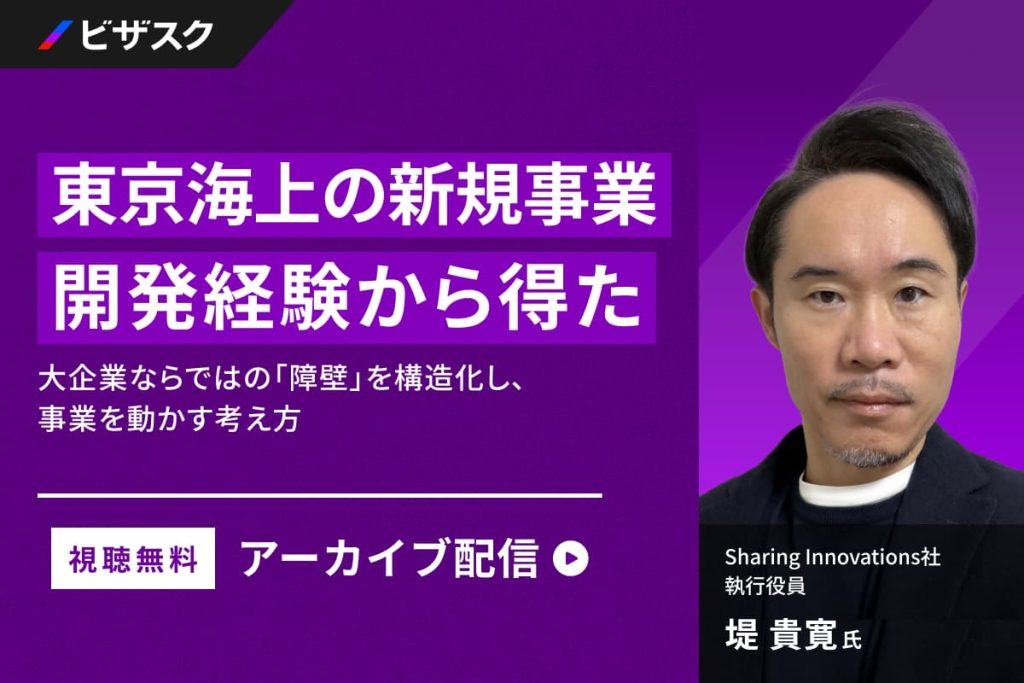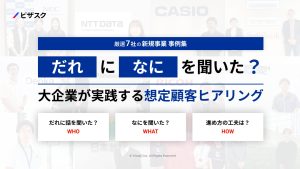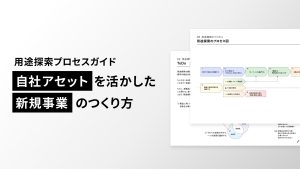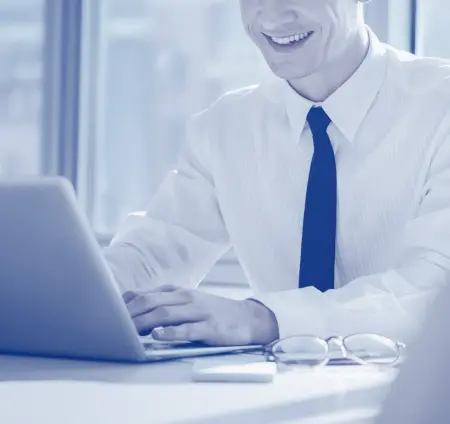有識者セミナーレポート
AGC新規事業担当者が語る
大企業×新規事業「両利きの経営」の実践
〜シリコンバレーやスイスでの取り組みから得られた教訓と経験知〜
近年、世界中で注目を集めている「両利きの経営」という経営論の書籍では、「既存事業のリソースを再活用して、新しい成長領域を見出す経営」の重要性が示唆されています。また、その実践の鍵は、「深化」させていくコア事業の組織システムと、「探索」していく新規事業の組織システムが異なる点をどう両立して経営するかにあります。
書籍の出版から時間が経ち、「両利きの経営」が広く知られるようになった一方で、「深化」と「探索」を両立させる組織をどのように作ればよいのかわからず、実践できてない企業は多いのではないでしょうか?
今回は、AGC株式会社技術本部企画部協創推進Gマネージャーの烏山純一氏をお迎えし、「両利きの経営」を実現するために大手企業が取り組むべきことについてお話いただいた模様をレポートします。
※本レポートは、2023年8月9日に開催されたセミナーをレポート化したものであり、当該時点での情報に基づき作成されております。
登壇者プロフィール
烏山 純一 氏
AGC株式会社 技術本部 企画部
協創推進G マネージャー
AGC(旭硝子)入社後、塗料用フッ素樹脂の新規事業の事業化・移管を担当。シリコンバレーの半導体スタートアップの日本事業立上げに貢献し、プリント基板の新規事業の立て直しに携わる。社費留学後に、新設の電子事業本部の長期経営ビジョン策定PJを企画主導しグローバル社内表彰で最高位の賞を獲得。シリコンバレーのソーラースタートアップとの新事業立上げを担当した後、スイスのナノテク開発スタートアップを買収・完全子会社化してスイスに駐在し同社CEOとして4年間PMIと共同技術開発をマネジメント。帰国後は経営企画と技術広報を担当した後、事業開拓部でオープンイノベーション創出活動を立案・遂行。昨年から研究所内のオープンイノベーション拠点を活用した、他社との協創による新規事業創出を目的とする新事業機会探索活動に携わる。
新規事業に必要な人財と組織
「マネージャー」と「リーダー」の定義について
今回は新規事業に必要な人財や組織についてお話させて頂きたいと思います。まず、日本の大企業の人財採用と育成の特徴についてお話させて頂きます。日本の大企業の採用は、グローバルな視点から海外と比較して見ると変わっています。新卒一括採用で、手厚い社内研修で、おおよそ5年くらいの時間をかけながら新入社員を育成していきます。また雇用形態はメンバーシップ制度が多く、ここも海外との大きな違いです。
大企業の新入社員育成の目標は「一流のマネージャー」を育て上げることであると思います。ここでリーダーシップ論のフレームワークをひとつ紹介させて頂きます。
この表はリーダーシップ論における、「マネージャー」と「リーダー」の定義を記したものです。例えば、マネージャーが「維持する」「管理する」ことを求められるのに対し、リーダーは「発展させる」「革新させる」といったことが求められます。大企業では、まずは一人前のマネージャーに育って頂くことを目指して、新入社員を育成していきます。
両利きの経営を実現するにあたって、必要となる組織カルチャー・運営形態、人財があります。両利きの経営には「深化」と「探索」という2つの要素があります。「深化」は既存事業、「探索」は新規事業です。それぞれで必要となる組織カルチャーが異なります。「深化」は大企業がやっているようなことに対して、「探索」は大企業の中でも小さな組織を立ち上げて始める、いわゆるスタートアップ的なカルチャーで取り組みます。
組織運営形態においても、「深化」を推進する既存事業では指揮をとる事業部長がいて、それぞれのパートを各メンバーが責任を持って運営する“オーケストラ”のような感じです。一方、「探索」を推進する新規事業は少人数でプロジェクトチームがスタートするため指揮者がいません。そのため、ジャズセッションのようにお互いの演奏を見ながら調整していきます。ここが先ほどのリーダーシップ論のフレームワークと少し重なると思っていて、「深化」を進めていくには一流のマネージャーであることが必要ですし、「探索」を進めていくにはリーダーの資質が必要になります。
大企業での教育にはいくつかの段階があると思います。新入社員に対して、まずは一流のマネージャーとしての資質を身に着けて頂いた上で、その次にリーダーとしての資質を磨いて頂く。そのうえで、さまざまな経験を重ねる事を通じて、新規事業を推進していく人財が育っていくのではないかと思います。
人財育成に関しても、ひとつのフレームワークを用いて説明します。これは人財の特性の3層構造というフレームワークです。「人間の内面はこうできている」というものを説明するためのモデルです。一番下にベーシックトラスト・基本的相互信頼関係があり、その上に思考特性や行動特性が、さらにその上にスキル・ノウハウがあります。
横軸は年齢です。ベーシックトラスト・基本的相互信頼関係は子どもの頃に築き上げられるものなので、会社は採用の前提として、これが備わっている人を採用することで育成の担保ができます。また、思考特性や行動特性として、マネージャーやリーダーになる教育をしていくのですが、これはあまり年齢を重ねると身に付かなくなるので、20代で会社に入り、40代までにこういった要素をインプットしていくことで身についていきます。
スキルやノウハウに関しての学習効率は若い頃の方がいいのですが、これは年齢を重ねても身につくものなので、長い目で見て身につけていく事も可能であると思います。
・・・(続く)
続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。