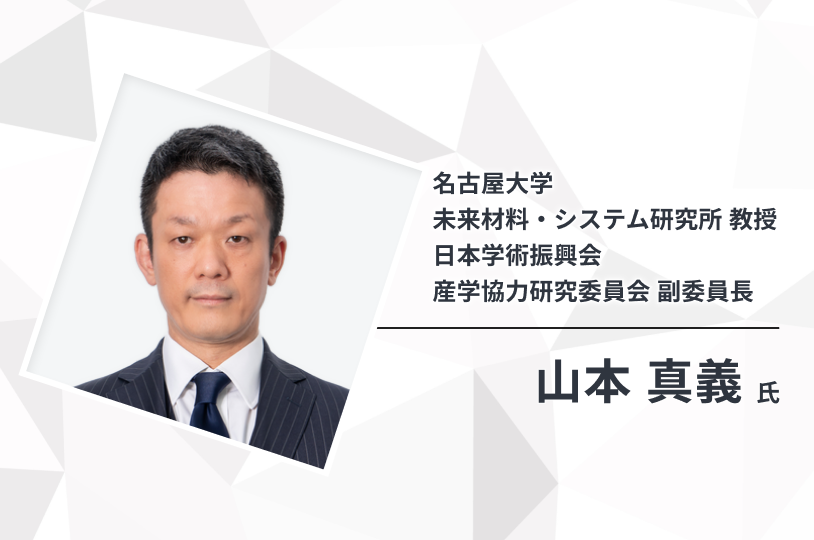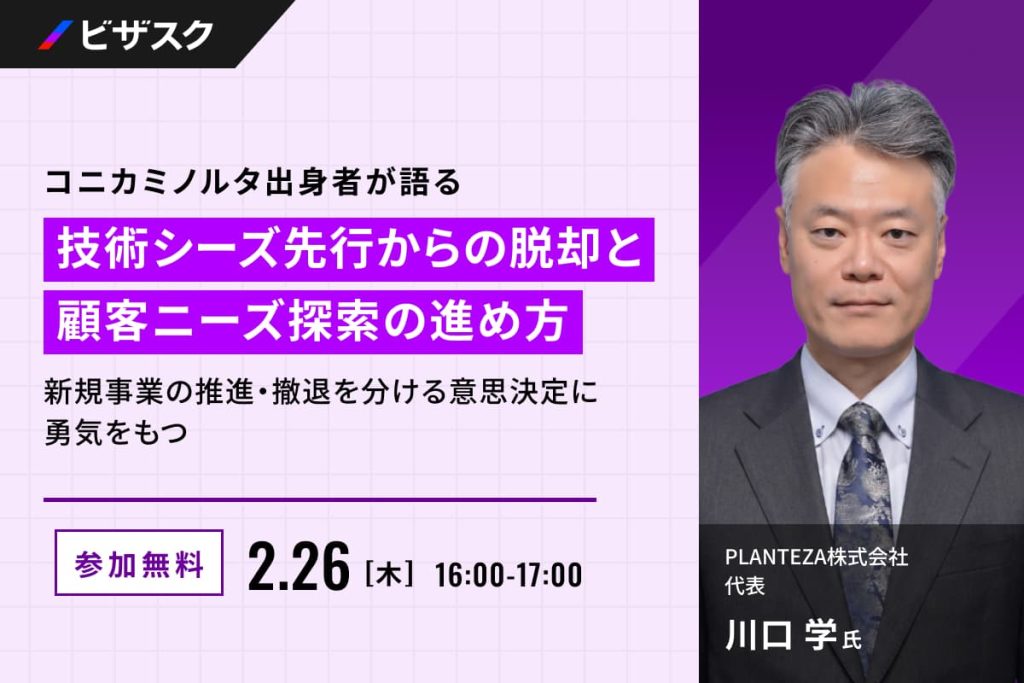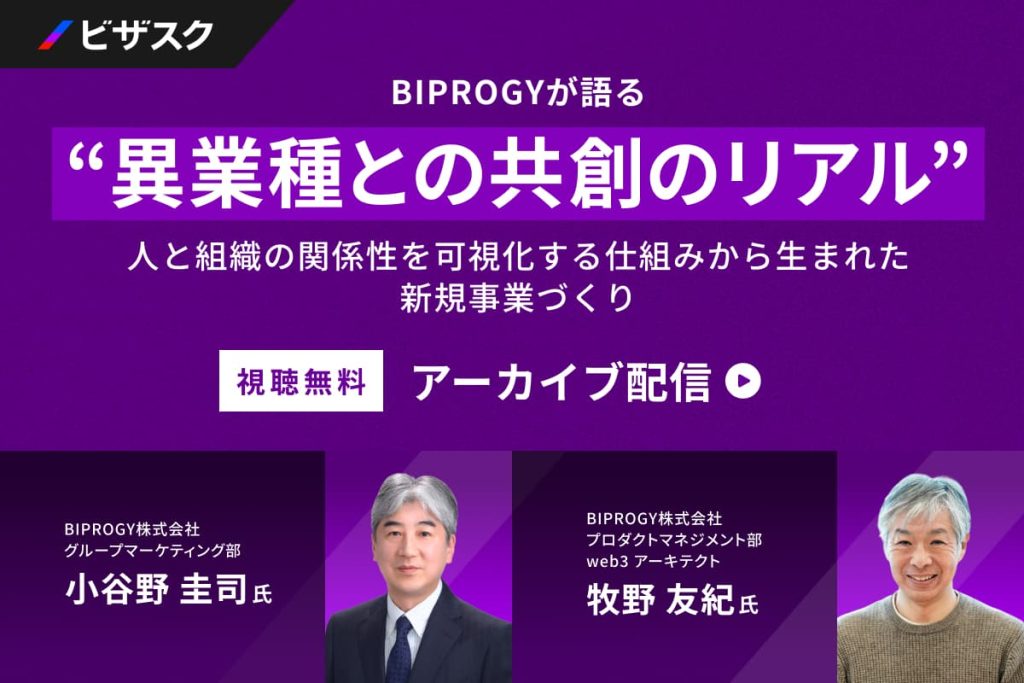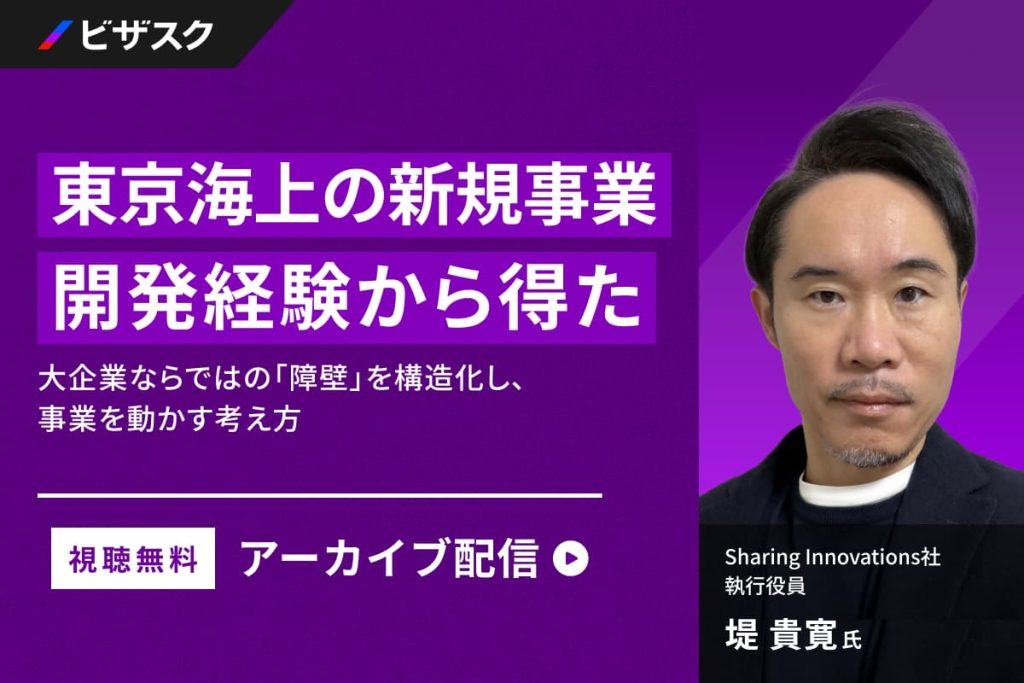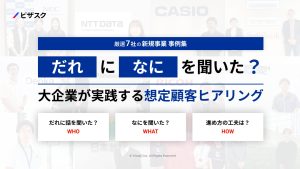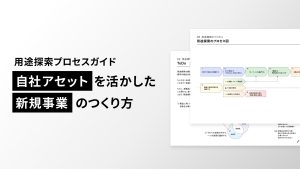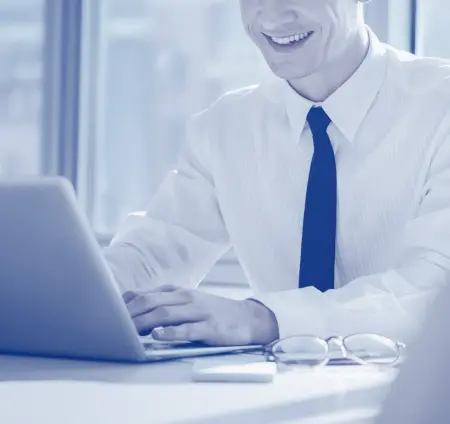有識者セミナーレポート
日米欧中のxEVの分解解析から読み解く
次世代自動車ビジネスの展望
〜パワー半導体を始めとした技術トレンドと、日本企業が掴むべき「勝機」とは〜
自動車業界において電動化という動きは、誰も止めることができない不可逆のトレンドにあります。自動車の電動化に向けた技術競争が加速する中で、自動車産業で求められているテクノロジーにはどのような変化や影響があるのでしょうか。また欧州や中国などのBEV先進国における最新テクノロジーの動向や日本企業が掴むべき勝機はどこにあるのでしょうか。
そこで今回は名古屋大学 パワーエレクトロニクス研究室の 山本 真義 氏 をお迎えし、xEVにおける各国・各社の技術動向や、パワー半導体応用技術、次世代自動車についてお話しいただいた模様をレポートします。
登壇者プロフィール
山本 真義 氏
名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授
日本学術振興会 産学協力研究委員会 副委員長2003年山口大学理工学研究科博士取得後、サンケン電気株式会社、島根大学総合理工学部 講師を経て、2011年より島根大学総合理工学部准教授着任。2017年より名古屋大学未来材料・システム研究所教授着任。パワーエレクトロニクス全般 (磁気、制御、回路方式、半導体駆動)に関する研究に従事。博士 (工学)。IEEE、電気学会、電子情報通信学会会員。応用は航空機電動化、自動車電動化、ワイヤレス給電の三本柱。日本の大学研究室としては珍しく、共同研究企業は40社を超え、海外の完成車メーカーとも強いコネクションを持つ。産学連携活動を強力に推進しており、企業との共同特許出願数も多数。共同研究だけでなく、各企業の戦略コンサルタントも請け負い、技術顧問としての活動も幅広い。
xEVの分解解析から紐解く、
各国のBEVに用いられるテクノロジーについて
電動車の技術ロードマップ
自動車業界の大きな流れとして、ホンダはGMとの量販価格帯EVの共同開発が中止になったことで、いま日産自動車と提携しようとしています。その狙いは何か。まさにプラットフォーム・パワートレーンの共通化にあります。例えば、BMWとトヨタのスープラが共通開発になっていますし、トヨタの86(ハチロク)とスバルのBRZは共通開発されています。
ただ、その中でも各社の色が出ています。
電動車における色とは何か。それは「E/Eアーキテクチャ」と呼ばれるものです。これは自動車に搭載されたECUやセンサー、アクチュエータなどを繋ぐシステム構造のことで、これが電動車における差別化ポイントになります。そこを全面に打ち出した自動車ということで、ホンダが開発を予定しているのはAFEELA(アフィーラ)です。
電動車に関しては、各国で開発のロードマップが異なります。中国は高圧系統に舵を切っており、欧州は新しい駆動方式による開発を模索しています。一方、日本は従来型のまま進化していく方向性になっています。
電動車は踊り場に来ていると言われていますが、今後揺り戻しが来ると思っています。自動車の販売数の見通しとして、トヨタが掲示した内容を見てみると、HEV(ハイブリッド自動車)が半数近くを占めています。これが2026年まで進むわけですが、2027年に日産とトヨタが同時に新しいバッテリーを出したときに、BEV(電気自動車)へのゆり戻しが1回来ます。そのときに備えて電動車への準備をしていくことが大切です。
ハイブリッド車も含めた電動車への準備をする、もしくは純粋な電気自動車についての戦略をとっていくかが各社求められることになっていきます。
電動車において、HEVもBEVも同じものが使用されます。バッテリー充電器もプラグインハイブリッドカーに使われているものを搭載しますので、エンジンがあるなしに関わらず充電器系の機構は必ず必要になります。電動化というアプローチのもとに企画戦略を立てていただければ、どちらにしても市場は拡大していくはずです。HEVが来るのかBEVが来るのか分からないから踏み込めないという人は、必ず膨れ上がっていく市場の商材に目を向けて研究開発のリソースを投下していくといいと思います。
BYDの市場戦略
昨今、中国のBYDが日本市場を攻めており、商材を拡販しようとしています。そんなBYDの強さはハイブリッドカーにあります。DENZAは見た通りですが、アルファードキラーと言われている車体です。SEALはインホイルモーターと呼ばれるものの前段の技術がそのまま使われています。日本のメーカーがまだ実現できていないところにBYDは挑戦していて、欧州系のメーカーと連動しながら新しい商材を開発しています。
中国系メーカーの戦略はインホイルモーターと高圧化が2本柱になっています。そこに日本が商材として入っていくのか、それともシステムとして対抗していくのか。今から考えていく必要があります。今日の議論の対象は「E-Axle」と呼ばれるものです。
E-Axleと呼ばれるものはテスラの モデルY に搭載されたものですが、モーター、インバーター、減速機と呼ばれる3つのシステムから構成されています。
これが汎用化されていく形で、ホンダと日産がプラットフォームを共通化していこうとしています。モデル3とモデルY は車体の性格は違うものですが、駆動自体は同じ。そのため、ホンダと日産がそれぞれ別の車でやっても、駆動は共通化していきます。
なおかつ、そこに使われるインバーターも共通化が進んでいます。2022年のモデルY を分解していくと、左側にモデル3と書かれています。つまり、モデル3のものを流用してもモデルYができるということです。ここの付加価値が下がっていくことによって、高温化と高圧化、自動運転の価値が高まる。そこに乗れるかどうかが大事です。
Xiaomi の SU7 とソニーのアフィーラを比較した注目ポイント
中国系の自動車といえば、Xiaomi という携帯メーカーがわずか3年で量産車を開発しました。このスピード感にはとても驚きました。いろんなキーワードがありますが、特に注目したいのが「Xiaomi Titans Metalを採用し」と書いてある部分です。ここには、Xiaomi Hyper Die-Cast と呼ばれるものが使われています。これを活用することで、重量を17%低減、量産工程時間を45%削減しています。AFEELAがどう対抗できるかが注目ポイントです。
Xiaomi は LiDARを搭載しているのですが、価格は452万円と非常に低価格です。彼らは付加価値をよく分かっていて、E-Axleと言われるものにお金をかけています。中国製のバッテリーはよく燃えるという噂がありますが、そこの技術力を担保していることも大きなアピールポイントになっています。
カメラとセンサーをここまで搭載している中、450万円という価格帯はセンセーショナルです。約1000万円と言われるAFEELAの半額でこれが実現できるのは恐ろしいところです。
特に中国で求められているのが計器ディスプレイやヘッドアップディスプレイ、センターコンソールへのインターフェースです。ここが中華系の電動車では付加価値になります。ソニーも強いのですが、インターフェースの大面積化へのアプローチが今から求められるようになります。Xiamoi の強みは自前でOSを持っていて、それを軸に人と車と家を連結できるところ。新しいライフスタイルを提案できるのがひとつの強みになっています。
日本は原点回帰が進んでいく中、中国と欧州は新しいエコシステムのインターフェースを軸に新規顧客を開拓していく動きになっています。
なぜ、Xiaomi は3年で開発できたのか。それはいろんなサプライヤーをかき集めて、組み合わせたからです。ただ組み合わせただけではなく、高電圧化など新しい技術を導入しながら組み合わせていきました。システム全体がわかる人材がきちんとサポートした結果です。
・・・(続く)
続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。