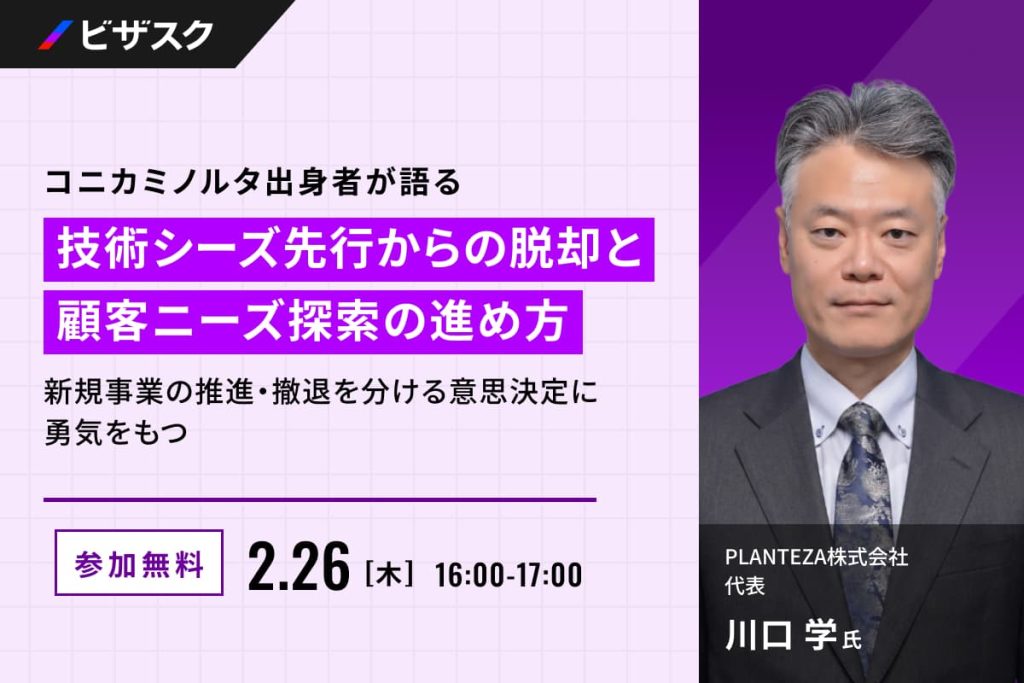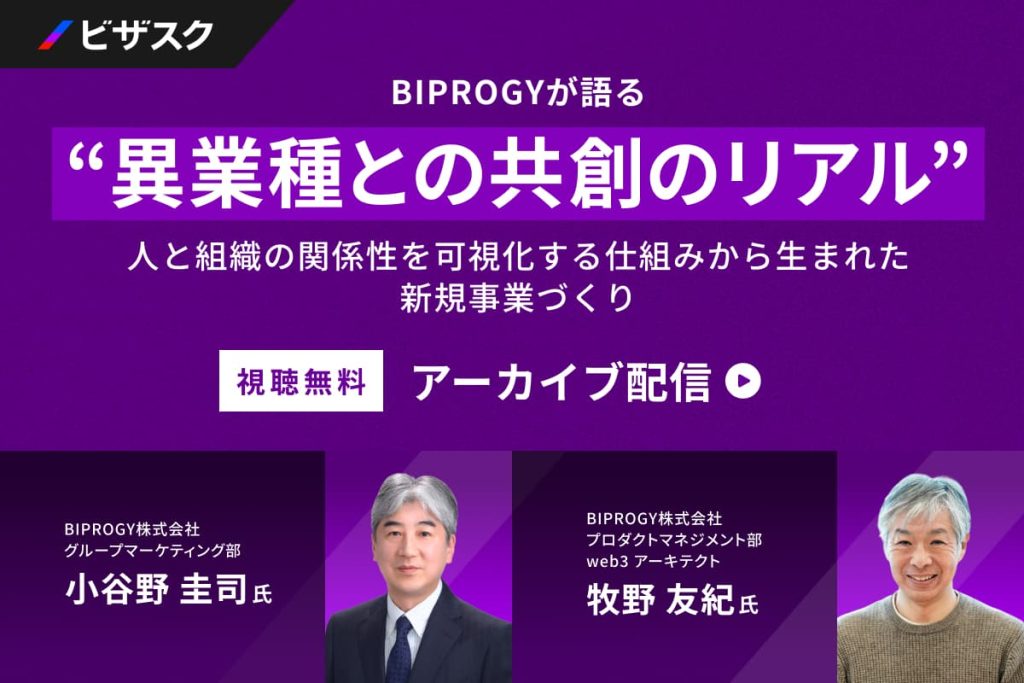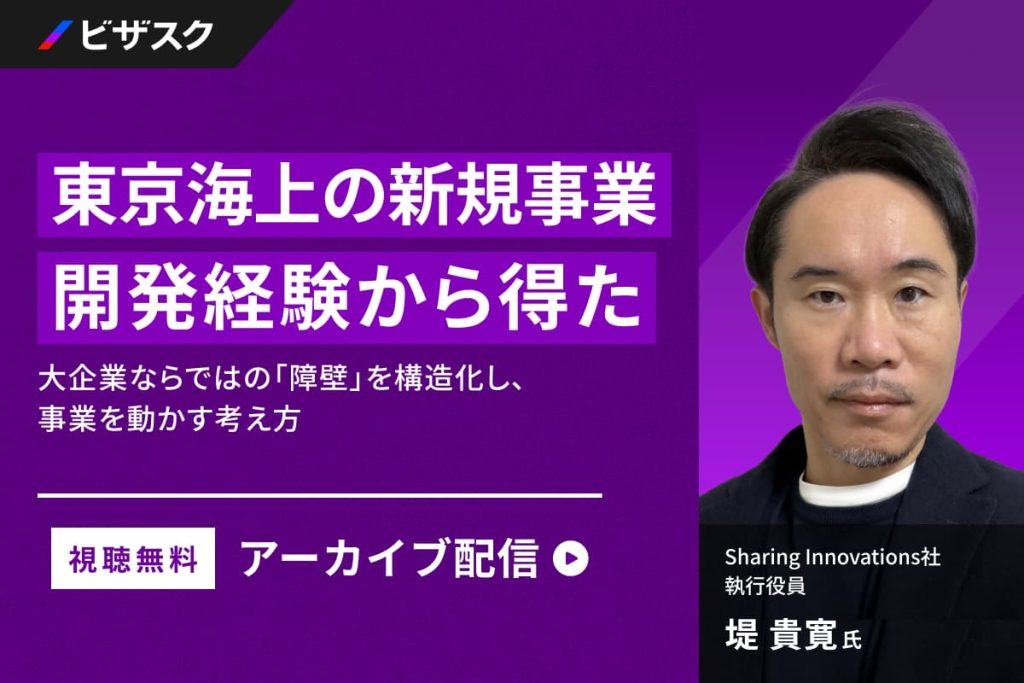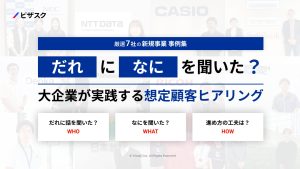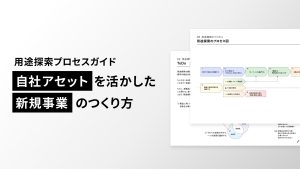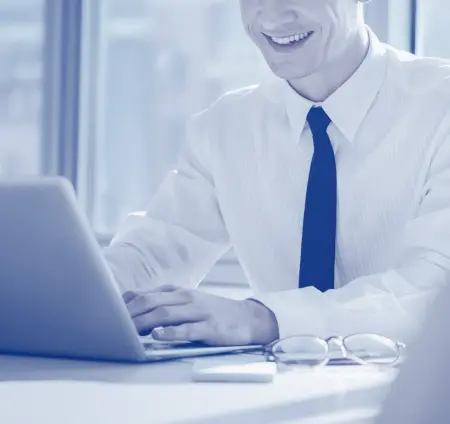有識者セミナーレポート
大企業からのイノベーション創出
ー新規事業を育てるカーブアウト戦略の実践ー
イノベーション創出や新規事業推進が一層求められる時代ですが、日本の大企業からは、なかなか
イノベーションが生まれていません。そのような中、既存事業の一部分を戦略的に切り出し、
社外事業として独立させる「カーブアウト」の動きが、大手企業の各社で見られます。
事務機器・光学機器の大手メーカーである株式会社リコーも、カーブアウトをイノベーション創出の手法として取り入れています。2019年、同社のカーブアウトの第一号として独立したのが360度カメラをコア技術とするベクノス株式会社です。
本記事では、ベクノス株式会社CEOの生方秀直氏をお迎えし、大企業が新規事業を推進する上での
カーブアウトについて、取り組みの背景や効果、課題などをお話しいただいたセミナーについて
お届けいたします。
登壇者プロフィール
⽣⽅ 秀直 氏
ベクノス株式会社 代表取締役 CEO(ご講演当時)
1989年株式会社リコー⼊社。商品企画、経営企画などを経て、同社の企業内起業プロジェクトを多数担当。ワンショットで360度の静⽌画や動画を撮影できる世界初の⺠⽣⽤全天球カメラ「RICOH THETA」のプロジェクトリーダーを務 め、2013年に商品化。今後も成⻑市場と⾒込まれている同市場の基盤を作り上 げた。2019年12⽉リコーを退社し、現職。(ベクノスCEO就任は会社設⽴の2019年8⽉から)
カーブアウトとは
ベクノス株式会社の生方と申します。当社は2019年、株式会社リコーから”スタートアップ”として
切り出された子会社です。
まず、カーブアウトとは何か。野村証券・証券用語解説集のシンプルな定義をお借りすると、
「会社分割の一種で、親会社が戦略的に子会社や自社の事業の一部を切り出し、
新会社として独立させること」で、”戦略的”というところがカギです。
実際に欧米では事業ポートフォリオを機動的に入れ替える手段として用いられています。
日本でもベンチャー企業を創設する際、カーブアウトを活用する事例が増えています。
ベクノスがカーブアウトした目的は、新規事業領域としての「映像関連コンシューマー・エンタメ事業」の創造です。将来的には、外部資金調達を目指しています。これから、カーブアウトという手段で
新規事業創出を目指す理由、戦略的意図やメリット・デメリットについて紹介します。
ベクノスと、360度カメラIQUI[イクイ]について
次に、我々ベクノスについて説明します。ベクノスは2019年8月に設立。同年10月にリコーからの投融資を受け、本格稼働開始いたしました。そして2020年、超スリム・ペン型360度カメラ「IQUI[イクイ]」を
開発、世界6カ国で発売開始いたしました。
「IQUI」のコンセプトは、360度カメラリクリエイションです。
360度カメラというと、業務利用が多いです。しかし、この面白い映像体験をより多くのお客様に楽しんでいただきたい、つまり360度カメラの民主化を実現したいと考え、改めてイチから見直してみることに
しました。単にカメラを創るのではなく、新しい映像体験を共有することにより、楽しみを広げていこうと考えたのです。
360度写真は、2013年発売の「RICOH THETA」でも撮影ができます。
しかし、我々は「IQUI」のコンセプトを実現するために、ゼロから技術開発を行いました。
「RICOH THETA」で薄型化のために開発した2眼屈曲光学系をあっさりと捨て、超スリム・ペン型のための4眼光学系を完全新規で設計したのです。
そして、肝となるのが「IQUISPIN[イクイスピン]」アプリです。
これは単独でも無料で利用でき、360度写真の標準フォーマットであるエクイレクタングラー形式を
サポート。「IQUI」以外の360度カメラからも読み込むことができます。
そして、360度写真からワンタッチでショートビデオを作成でき、SNSなどで簡単にシェアできます。
こうした新しい映像体験や感動を提供しています。
ありがたいことに、「IQUI」はグッドデザイン賞など、様々なデザイン賞を受賞しました。
現在、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、中国の6カ国で販売中です。
大企業の新規事業開発
ここからは、会社を切り出した理由も含め、カーブアウトについてお話しします。
カーブアウトには、「再成長戦略型」「新規事業創造型」2つの類型があると私は考えています。
既にキャッシュフローが成立している事業を切り出してもう一度成長させていこうというものは
「再成長戦略型」となりますし、これから新しく事業をインキュベートしようというものについては
「新規事業戦略型」となります。
大企業で新規事業を開発するメリットは、まず何といっても規模の大きさです。
懐が深く、多様なアイデアを試す”隙間”があります。人材も豊富で、外部とのコネクションも広く厚く、
何か新しいことをしたいとき、縦横無尽に声を掛けてプロジェクトを構造化することが可能です。
そして雇用が比較的安定していることから、安心してチャレンジすることができます。
つまり、可能性・オポチュニティーの宝庫ですね。
一方で、陥りがちな状況もあります。「大企業病」とよく言われますが、プロジェクトが拡大するほど、
大企業ならではの意思決定プロセスが重くのしかかります。
そして、新規分野になるほど全社としての位置づけが難しく、責任が宙に浮きがちです。
また、コア事業が強いほど、その文化や特質の影響を強く受け、新しい動きが難しくなります。
現代的な手法としてクラウドファンディングなどの事業化前テストマーケティングアプローチもありますが、事業黒字化の担保は難しいという問題もあります。
さらに、上場企業の場合は特にP/Lベースの経営管理が価値基準となる場合が多く、事業化した瞬間から
P/Lとの闘いが始まることも厄介です。
新規事業開発・事業化組織体のフレームワーク
新規事業開発の枠組は、いくつかあります。
母体会社との関係性が密な順から、「既存事業部内」での実施、「社内ベンチャー」として独立組織を
立ち上げる、「子会社」として切り出す、「JV・関連会社」として他社の資本も含めて設立、そして「カーブアウト」として外部資本を多く入れる、さらには「スピンオフ」、「スピンアウト」といった方法があります。
・・・(続く)
続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。