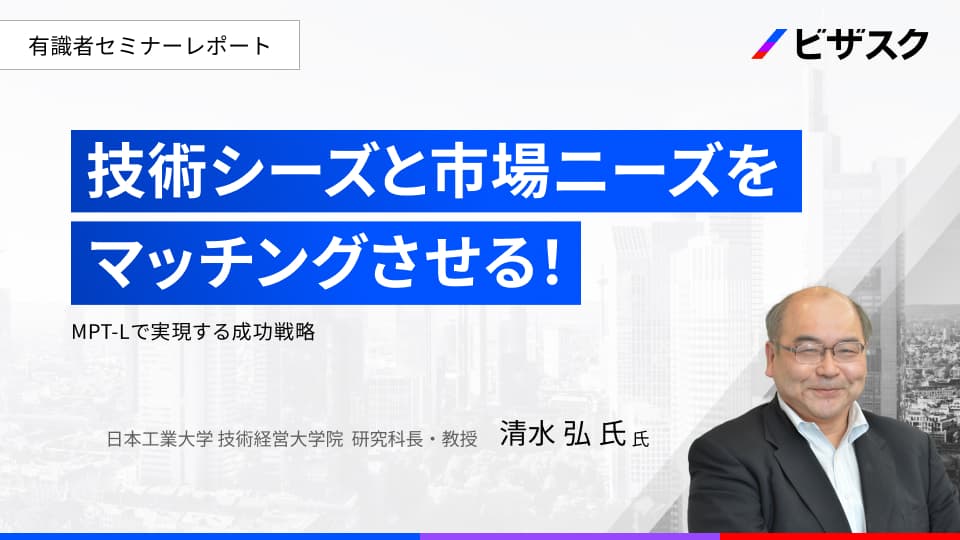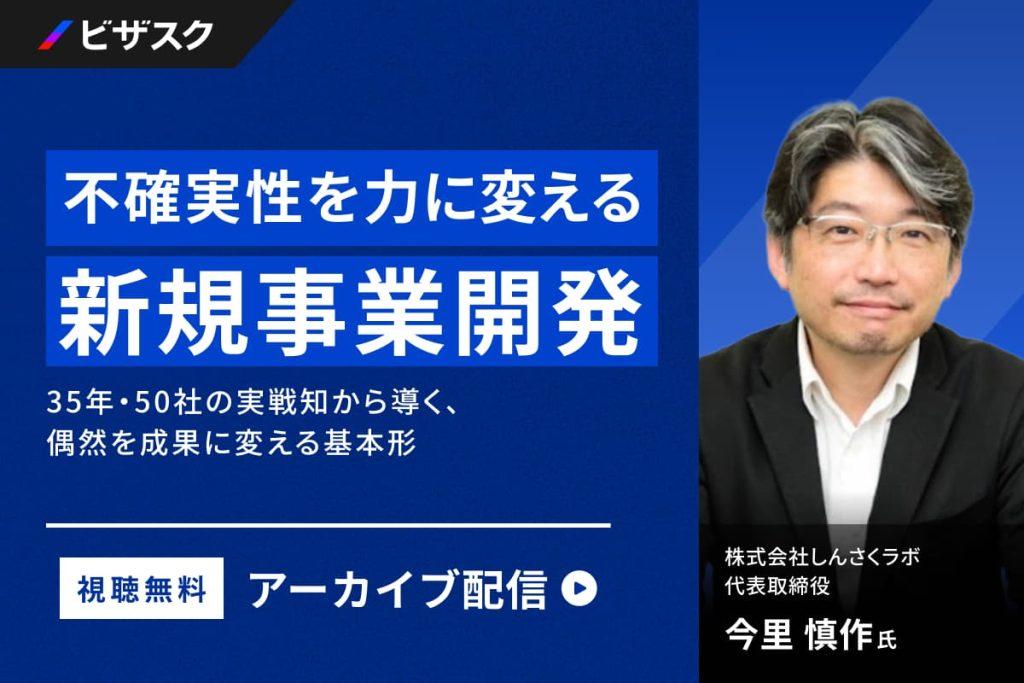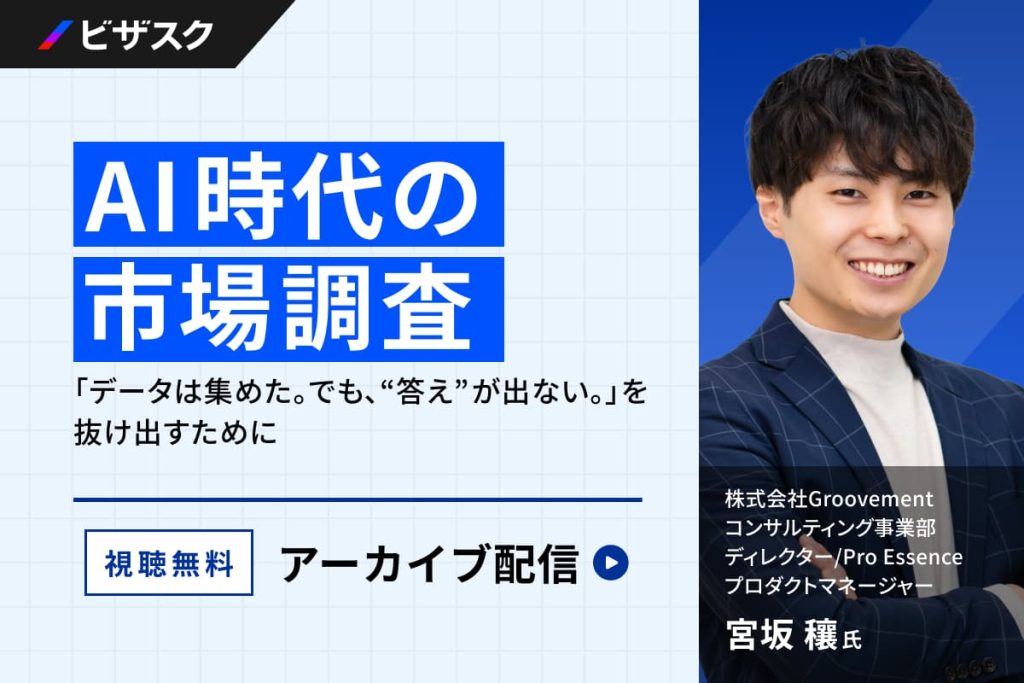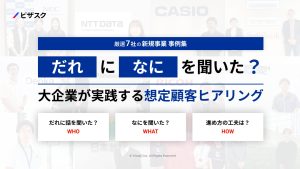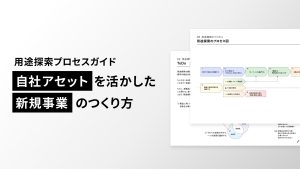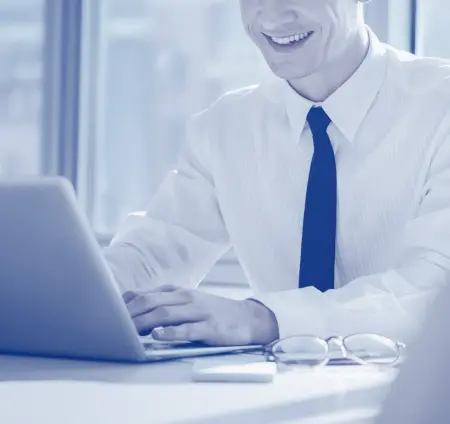有識者セミナーレポート
製造業のための技術マーケティング
技術シーズと市場ニーズをマッチングさせる!〜MPT-Lで実現する成功戦略〜
技術開発や研究の成果を市場に適用する際や、既存事業の製品展開を進めて行く際に、技術シーズと市場ニーズの間にギャップを感じることは少なくありません。
そこで今回は、日本工業大学 技術経営大学院 研究科長・教授の 清水 弘 氏をお迎えし、技術マーケティングの体系的手法「MPT-L」を活用して技術の強みを活かしながら市場価値を創出する方法について紹介いただいた模様をレポートします。
登壇者プロフィール
清水 弘 氏
日本工業大学
技術経営大学院 研究科長・教授東洋エンジニアリング㈱で化学プラントの設計を経験後、1990年より技術と経営の融合を目指す戦略コンサルティング企業のアーサーDリトル社(ADL)に参画。製造業を中心にIT企業、サービス業の戦略、技術、組織の経営課題の解決に従事。2002年よりディレクター/パートナー。2012年から日本工業大学技術経営大学院で技術と経営に関する教育と研究に従事し、2022年より研究科長(現任)。また、ビジネスエンジニアリング㈱社外取締役、中堅素材企業監査役や中国自動車部品企業CEOアドバイザーにも就任(現任)・京都大学工学部合成化学科卒業。
技術マーケティングの重要性と従来マーケティングの問題点
膨らみの機会の構想へ
今日は技術を活かすマーケティング手法として、日本工業大学の技術経営大学院(MOT)で活用しているMPT-L(Market/Product/Technology-Linkage)という手法を中心に紹介していきたいと思います。大きく3つの内容にわけて、話を進めていきます。
1つ目が「技術マーケティングの重要性と従来のマーケティングの問題点」について。2つ目が「技術を活かすマーケティング手法とMPT-L」について。そして、最後がMPT-Lの活用について、具体的にどのような方法があるかの話をしていければと思っています。
まず技術マーケティングの重要性について、いまさら申し上げることもないかなと思いますが、中国企業を筆頭にキャッチアップの早い競合が生まれ、市場が速いスピードで変化していく中、日本企業としては膨らみの機会を構想し、それを実現することが求められるようになっています。
では、膨らみの機会をどう見つけていくのか。大事なのは将来指向で、政治、経済、社会、技術の変化を先読みし、自社の機会をストーリーとして示すことです。その上で、従来は国内中心で考えていけば良かったのですが、今はグローバルに多様な地域の顧客と競合の動向を、市場と技術の視点で理解し、自社の意思決定を推進することが求められています。
グローバル視点と国内視点のバランスをどう取っていくか、という点においては難しい状況になってきたな、と感じています。それから、自社・自組織の状況や位置づけにあった既存・新規や攻め・守りの製品・市場展開をしていく必要もあるでしょう。
今回は競合との差別化という上で、ソリューションという言葉を使わせてもらっています。市場と技術の理解によるソリューションの先行が不可欠となっており、BtoB企業の場合は顧客の仕様決定に関与することでのプレミアムを提供することが重要です。
こういったことを行っていきながら、体系的に膨らみの機会を捉えていくということが、これまでになく求められる状況になっていると考えています。そういった中で、今日ご参加されている方の中には技術者ではない方もいらっしゃるかと思いますが、技術者のマーケティングという観点で申し上げさせていただくと、やはり技術を知らない方のマーケティングは、特に製造業やBtoBの企業の場合、やや限界があると考えています。
技術者がマーケティングを理解をする方が、マーケティングの専門家が技術を理解するよりも早いと言えるのではないかと思っています。マーケティングの大切さは、今さら言うまでもないことだと思いますが、シーズ・アウト型のプロダクトであったとしても、市場獲得や成長継続にはマーケット・イン型のプロダクトに移行させる必要があります。シーズ・アウト型、マーケット・イン型でも技術が必要なことは、もう言うまでもないでしょう。
技術なしの場合、プロモーションやチャネルを工夫するといった形だけではすぐに限界を迎えてしまいます。技術者のマーケティングを考えていったときに、やはり技術者ならではのマーケティング手法というものがあるかと思います。
技術者がマーケティングを行うことのメリットは、長期的な技術の変化を理解をして、市場、顧客に将来的な展望を示せることが一つあると思います。また、市場、顧客のニーズの解決は、トレードオフ(二律相反)になってしまうことが多いんですね。例えば、品質を高めようとしたらコストがかかってしまう。二律相反という問題がある中で、ニーズの重要性を理解した上で、技術の選択をするということが大変重要になってきます。
もう一つの視点としては、お客様は問題を解決できそうな人にしか問題を話さないということがよくあります。
例えば、営業の方、技術の方が一緒に訪問していった場合と、営業の方だけで行った場合では、お客様の会話内容が変わってくることがあるかと思います。そういった意味では、技術者がいることによって、この人なら問題解決ができそうだなということがわかることによって、ちょっと違った話が聞けるということがある。専有情報というふうに呼んでますが、そんな情報にアプローチしやすいという特徴があります。
ただ、注意しなければいけないのは、技術者の方は、マーケティングだけではなくて、技術開発、製品開発など、様々な活動を行っていく必要があるということで、マーケティングに優先順位を置きにくいということもあるかと思います。
マーケティングは、お客様にアポイントメントを取るなど大変な作業をやらないといけないのですが、そういったことはやらずに、技術開発や製品開発の方に時間を使ってしまう。「技術に逃げる」という側面もあるのかなと思っています。そういう意味でも、技術マーケティングを理解した、技術者のマーケティングは重要なことだろうと思っています。今日のお話が皆さんのマーケティングをさらに深めていく上での参考になればと思います。
無形なアイデア・技術から儲けるまで
では、どういう考え方で進めていけばいいのか。基本の流れは、アイデアを様々な形でマーケットニーズと技術・資源のシーズ等を組み合わせをしながら、プロダクトとして具体化をしていく。これを市場に投入し、市場を拡大成長させていくという一連の活動となります。無形なアイデア、アイデアの中にはもちろん市場ニーズも技術シーズも含まれますが、これをお金に変えていくという活動というのが、価値創出活動だというふうに言って良いかと思います。
上段の方に市場・顧客ニーズと、下段の方に技術・資源シーズというふうに記入させていただいてますが、このマッチングが重要であることは言うまでもないでしょう。このマッチングをどうやってるかというと、実際は多段階の活動が進んでいると思います。
・・・(続く)
続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。