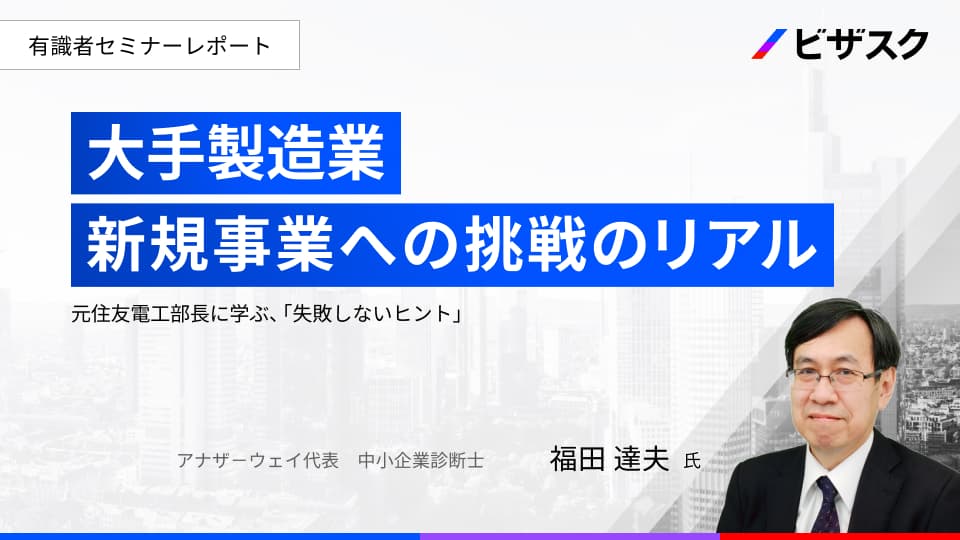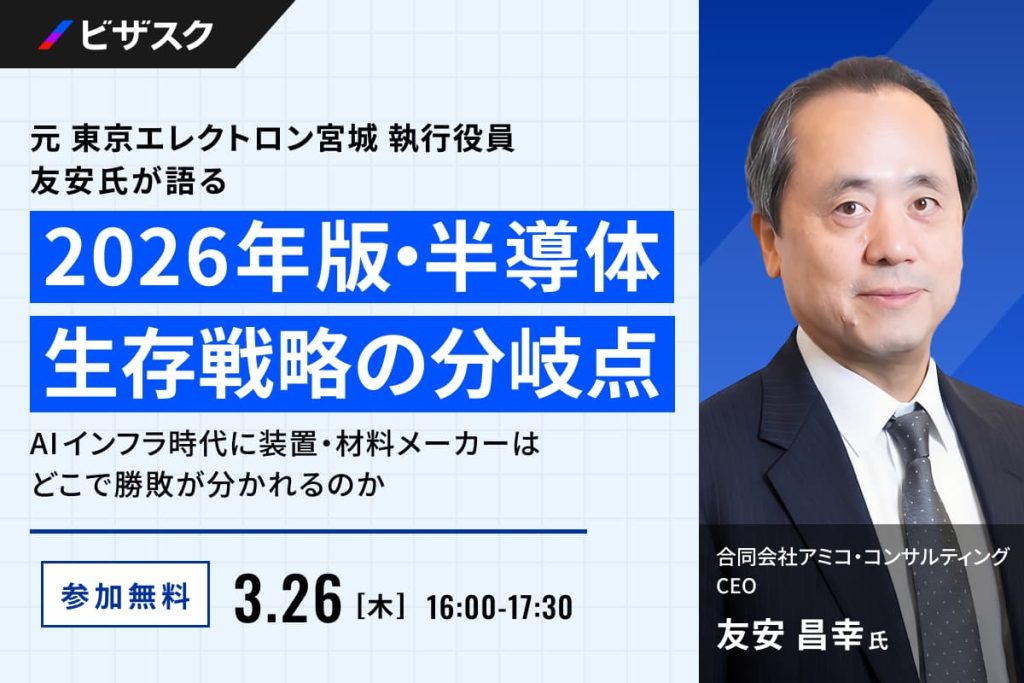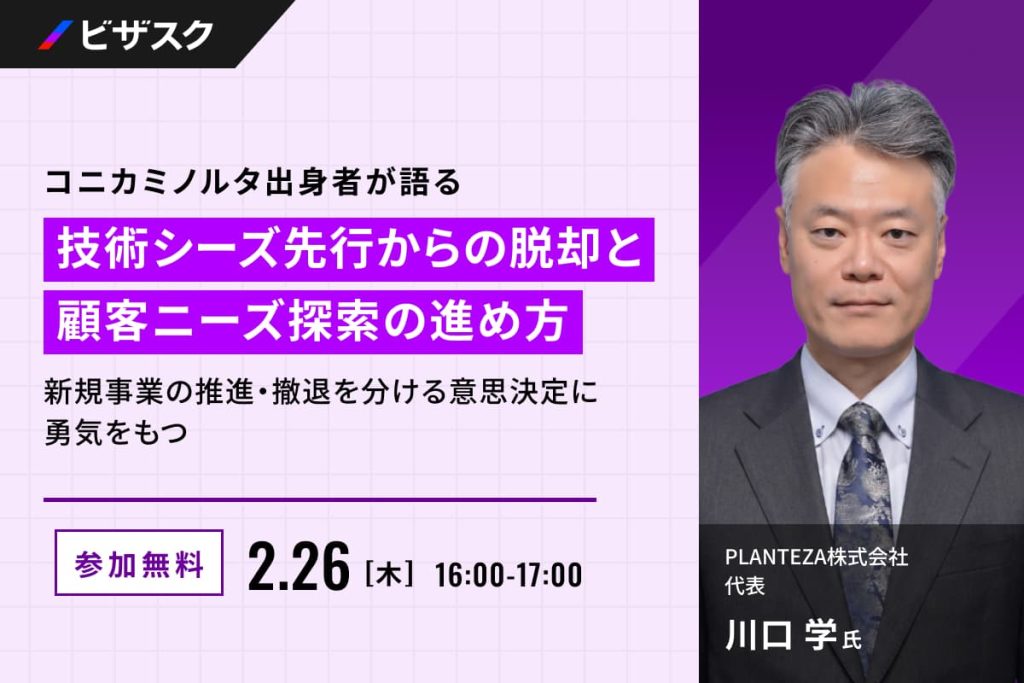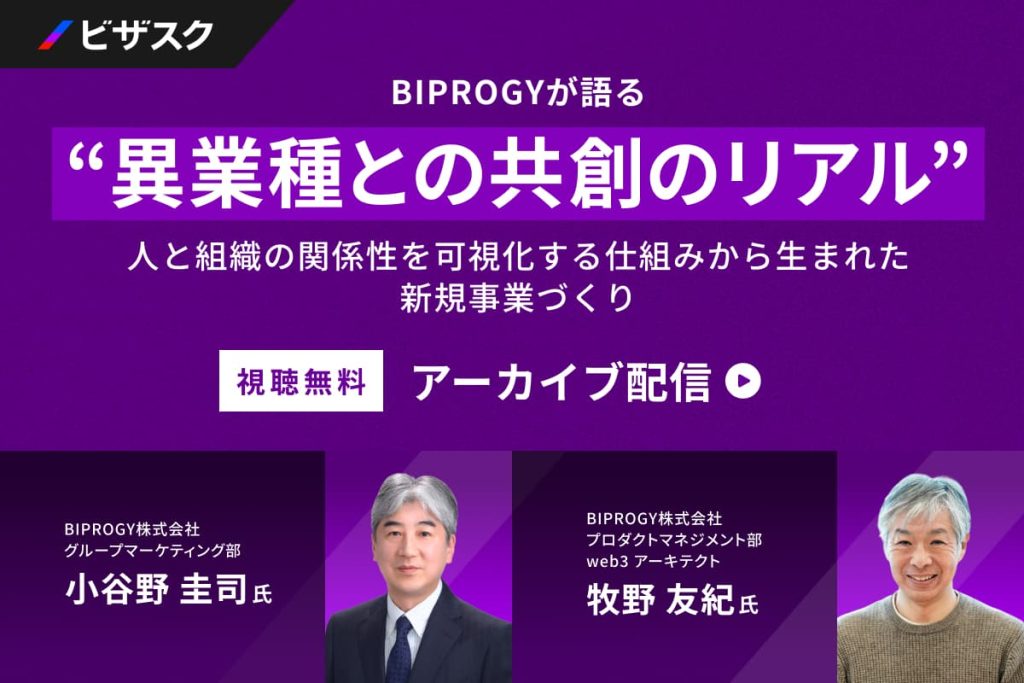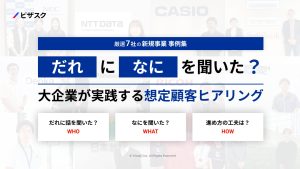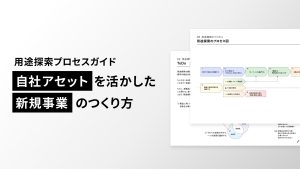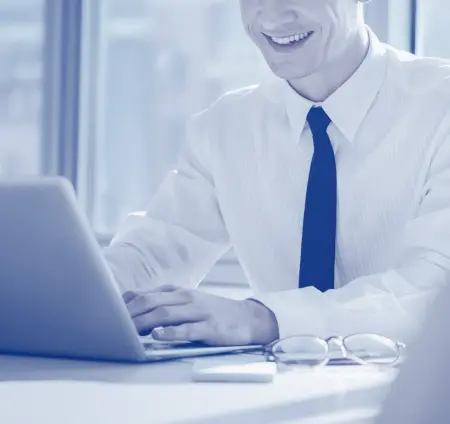有識者セミナーレポート
大手製造業 新規事業への挑戦のリアル
〜元住友電工部長に学ぶ、「失敗しないヒント」〜
多くの⼤⼿製造業において、新規事業の創出は企業の持続的成⻑に不可⽋なテーマと認識されています。しかし、既存事業が盤⽯であるゆえの危機感の乏しさや、⽣産⽴ち上げまでに多⼤な時間と資⾦を要する特有の事情から、その道のりは決して平坦ではありません。スタートアップや⾮製造業のセオリーがそのまま通⽤しない世界で、ご担当者は⽇々もがきながら事業化への険しい道を歩まれていることと存じます。
本レポートは、住友電気⼯業株式会社にて11年間にわたり新規事業開発本部の初代企画業務部⻑として複数事業の⽴ち上げと撤退を経験された福⽥ 達夫⽒にご登壇いただいたセミナーの様⼦をレポート化しました。⼤⼿製造業のリアルな現場から得られた「失敗しないためのヒント」を、戦略、数値管理、そして⼈材育成という多⾓的な視点から紐解いていきます。福⽥⽒が語る⽣々しい経験談と実践的な知⾒は、新規事業に関わるすべての⽅にとって、⾃社の取り組みを成功に導くための羅針盤となるはずです。
登壇者プロフィール
福⽥ 達夫 ⽒
アナザーウェイ 代表/中⼩企業診断⼠
1982年、住友電気⼯業株式会社に⼊社後、既存事業部の企画業務部⾨、関係会社⼈事総務マネジャー等を経て、2013年、新規事業開発本部の発⾜に伴い、初代企画業務部⻑に就任、在任11年間で複数事業の⽴ち上げ、撤退を経験。 新規事業活性化に向けた社内⾵⼟改⾰、⼈材コミュニティ構築にも注⼒。2024年、定年退職に伴い、アナザーウェイ(コンサルティング個⼈事業)開業。著書「知りたい! ビジネスキャリア制度」、他共著多数。
第1章:新規事業経験からの学び
戦略上の判断ポイント
新規事業を進めていく上で、当初思い描いていたストーリー通りに進まず、戦略上重要なストーリー変更などを余儀なくされることがあります。特に製造業の新規事業では、同様のことにぶち当たる可能性が⾼いと考えられるため、私が経験した3つの判断ポイントをご紹介します。
1. 参入レイヤーの問題
例えば、私が関わったある合金の事業では、当初、素材(板材)でPCメーカーに参入するストーリーを描いていました。その合金の売りである「軽量化」を事業のメリットにできるのは最終製品メーカーであるPCメーカーです。しかし、PCメーカーは板材を直接仕入れることはなく、板材を筐体に加工した中間財メーカーから筐体の形で買うというサプライチェーンが確立されていました。
では、中間財メーカーに板材を売ればいいかというと、彼らはわざわざ実績のない素材に切り替えるメリットがありません。結果として、私たち自身が中間財メーカーの土俵、つまり経験の少ないプレス加工を自社で行い、筐体にして納入せざるを得なくなりました。
一般に川上(素材)より川下(中間製品)の方が付加価値は高いですが、素材メーカーが川下に参入するには、新たな技術習得が必要になり、不得意な方向に戦線が拡大することになります。ここでは「評価してくれる人(PCメーカー)」と「買う立場の人(中間財メーカー)」が不一致であるという問題が起こりました。
2. 顧客の意思決定者の問題
「評価してくれる人と買う立場の人の不一致」は、顧客企業内でも起こり得ます。新規事業部門が持ち込む製品を最初に評価してくださるのは、多くの場合、顧客の開発部門です。開発部門は新しいものを使ってみたいという潜在的な希望を持っているため、私たちの新製品に「いいね」と言ってくれるハードルは低く、コスト増にも比較的寛容です。
しかし、量産品への採用を決定するのは設計部門や購買部門です。彼らの立場からすれば、新製品の採用はリスク以外の何物でもありません。コストが下がるならまだしも、仕入値が上がりリスクが増えるのであれば、採用判断が厳しくなるのは役割として当然のことです。このように、開発部門で試験採用されれば本採用は目前、という当初の想定は覆され、量産採用までの道のりは難航しました。
3. 生産キャパの問題
新規事業の当初は、リスクを抑えるために最小限の生産キャパでスモールスタートしたいと考えます。しかし、発注してくださる製品メーカーにすれば、その製品がもしヒットしたら一気に市場投入したいわけですから、増産に対応できるレベルのキャパを用意してもらわないと発注できない、ということになります。
結果として、私たちは参入当初から受注確定分の数倍の生産キャパを用意せざるを得なくなりました。特にBtoBの製造業では、当初のキャパは自分の都合では選べず、スモールスタート自体が難しいと考えておいた方がいいかもしれません。
これらの判断ポイントは、後から振り返ると「スモールスタートすべきだった」など結果論になりがちです。しかし、当時の状況を考えれば、その判断はやむを得ない事情があったのも事実です。何が正解か決めることは難しく、立場の違う人も含めて色々な知見を入れ、しっかり考えることが必要です。
業績数値管理
走り出した事業がうまくいっているかは、業績数値、具体的には事業計画と実績の対比によって定量的に判断します。既存事業であれば計画と実績が合うのが当たり前で、精度は90〜95%以上ある感覚ですが、新規事業では合わなくて当たり前、桁違いもあり得ます。
その要因は「多すぎるタラレバ」にあります。新規事業の事業計画をよく見ると、「歩留まり〇%が達成できれば」「売値〇円が容認されれば」といった、達成ハードルが非常に高い仮説がいくつも重なっています。いわば「タラレバの6乗」のような事業仮説が、いつのまにか事業計画として独り歩きしてしまうのです。
このタラレバは、目に見えない形で隠れていることもあります。例えば、新規製品のコスト想定で使われる「量産時推定」という言葉。これには「受注目標が100%達成できた前提の生産数量」や「それに見合った大量仕入れによる原料費減」「歩留まり向上」など、いくつものタラレバが織り込まれています。さらに受注目標自体が「市場予測 x 想定シェア x 想定売上単価」で算出されていたりすると、実は「タラレバの9乗」だった、ということもあり得るのです。
多すぎるタラレバとその克服(仮説指向計画)
この「多すぎるタラレバ」をどう克服すればよいのでしょうか。まず、複数の仮説が重なると達成確率が著しく下がることを認識する必要があります。例えば、達成確率80%の仮説が6つあると、事業仮説全体が実現する可能性は26%しかありません。
この問題を克服するには、メンバー全員で「タラレバ」を共有し、見直し、修正を繰り返すことが必須です。そのための有効なメソッドが「仮説指向計画」です。これは、事業の成功に必要な条件を「仮説」として明確にし、仮説は外れるものとして継続的に管理することで、環境変化に対応して次の一手を早期に促す考え方です。
まず、事業計画の根拠となる数値を「仮説」として一覧にし、設定根拠(標準値、最低値、最高値)を見える化します。次に、事業部門と管理部門が「管理する‧される」の関係ではなく、対等なコミュニケーションを通じて、仮説と実績の乖離を定期的に確認し、見直すサイクルを回します。 これは「力を合わせて、必死に考え続ける仕組み」です。
仮説指向計画で特に有効なのが、感度分析を可視化する「トルネイドチャート」です。これは、各仮説が事業の損益に与えるインパクトの大きさをグラフにしたもので、どの仮説が最も重要かが一目でわかります。私が経験したある事業では、トルネイドチャートが左方向(マイナスインパクト)にばかり伸びており、計画が非常に危うい状態であることが視覚的に確認できました。不確実な事業に対して仮説指向計画は有効であり、まずは仮説の抽出とトルネイドチャートの作成からでも実践をお勧めします。
黒字化より手前に置くべきマイルストンとは
新規事業のマイルストーンとして「単年度黒字」が掲げられますが、特にBtoB製造業では、これは遠すぎる目標ではないかと考えています。初期投資の償却費などが重くのしかかるからです。
そこで私が注目したのが、「売上高と同額以下の赤字」を一次マイルストンとして設定することです。これは、「売上高が総原価の半分」であり、「総原価が売上の2倍」である状態を意味します。
このマイルストンには2つの意義があります。
- 一定レベルの実需の存在が確認できる:売上が総原価の半分はあるということは、売上が全く足りないわけではない、ということです。
- 黒字化への道筋が見える:総原価を半分に圧縮すれば黒字化できる、ということで、具体的‧達成可能な目標設定が可能になります。
過去の事業を振り返ると、このマイルストンをクリアした事業は、その後黒字化に向かう傾向がありました。遠い「単年度黒字」を目指す前に、この達成可能な中間目標を意識してみてはいかがでしょうか。
第2章:新規事業にはエフェクチュエーションを併用
既存事業だけでなく、新規事業でも、最適な計画を立てて実行する「コーゼーション(因果論)」が基本ですが、ターゲットが不明確であったり、環境予測が難しかったりする新規事業特有の状況も多くあります。こうしたコーゼーションだけでは解けない不 確 実な状 況を打 開するために知っておきたいのが「エフェクチュエーション」という考え方です。
これは、成功した起業家たちの意思決定の論理を体系化したもので、5つの原則からなります。
- 手中の鳥の原則 (Bird in Hand): 目的から始めるのではなく、今ある手持ちの手段から着手します。手持ちの手段とは、「私は誰か(アイデンティティ)」「何を知っているか(知識‧経験)」「誰を知っているか(人脈)」という3つのカテゴリーと、「余剰資源(遊休設備や空き時間など)」からなります。まずは自分のリソースを棚卸しすることから始まります。
- 許容可能な損失の原則 (Affordable Loss): どれだけ儲かるか(期待利益)ではなく、最悪の場合に失う損失が許容できるかに基づいてコミットします。起業家でも命がけのジャンプはしません。失敗しても再チャレンジできる範囲で行動することで、新しいことを始めるハードルが低くなります。
- レモネードの原則 (Lemonade): 予期せぬ事態や失敗を避けるのではなく、むしろ偶然をテコとしてポジティに活用します。「酸っぱいレモン(失敗作)を手にしたら、美味しいレモネードを作ればいい」という発想です。3M社のポスト‧イットが、強力な接着剤開発の失敗から生まれたのは有名な事例です。
- クレイジーキルトの原則 (Crazy-Quilt): 競合を分析するのではなく、自発的に関わってくれる人たちとパートナーシップを構築します。様々な人やリソースが加わることで、スタート時には思いもよらなかった形に事業が仕上がっていく様が、パッチワークキルトに例えられています。完成図が決まっているジグソーパズル(コーゼーション)とは対照的です。
- 飛行機のパイロットの原則 (Pilot-in-the-plane): 未来を予測するのではなく、コントロールすることで望ましい未来を自ら創り出そうとします。自動操縦(コーゼーション)に任せるのではなく、パイロットである自分が主人公となり、状況を見ながら自ら操縦桿を握るイメージです。
この5原則は、例えば私の知人が経営する会社の事例にも当てはまります。彼は紳士服店を継ぎましたが、市場縮小により廃業を決断。しかし、手持ちの手段(都心の一等地にある店舗、自身のIT技術)を活かしてインターネットカフェを開業し、そこでの偶然の出会い(近隣オフィスの客とのパートナーシップ)をテコに、現在はシステムサポート業へと業態転換を果たしています。
・・・(続く)
続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。