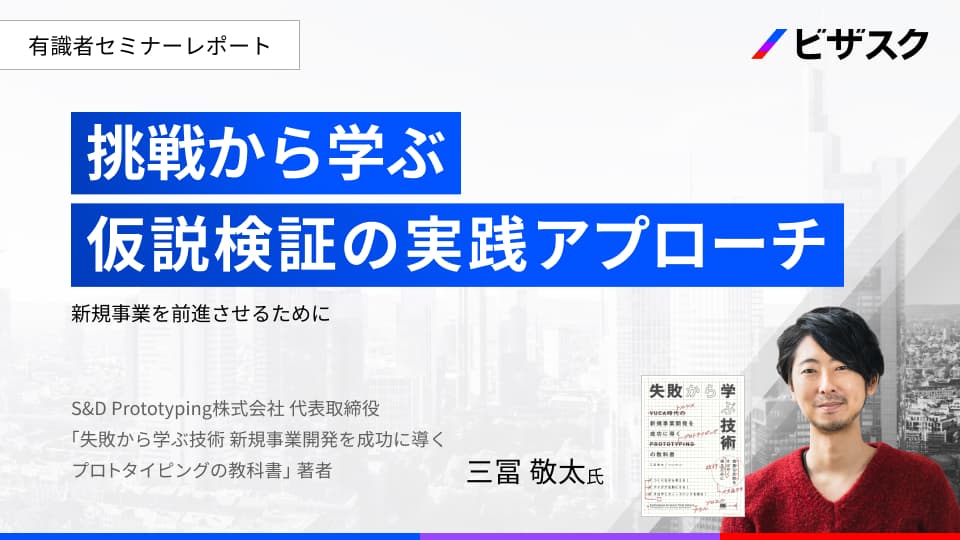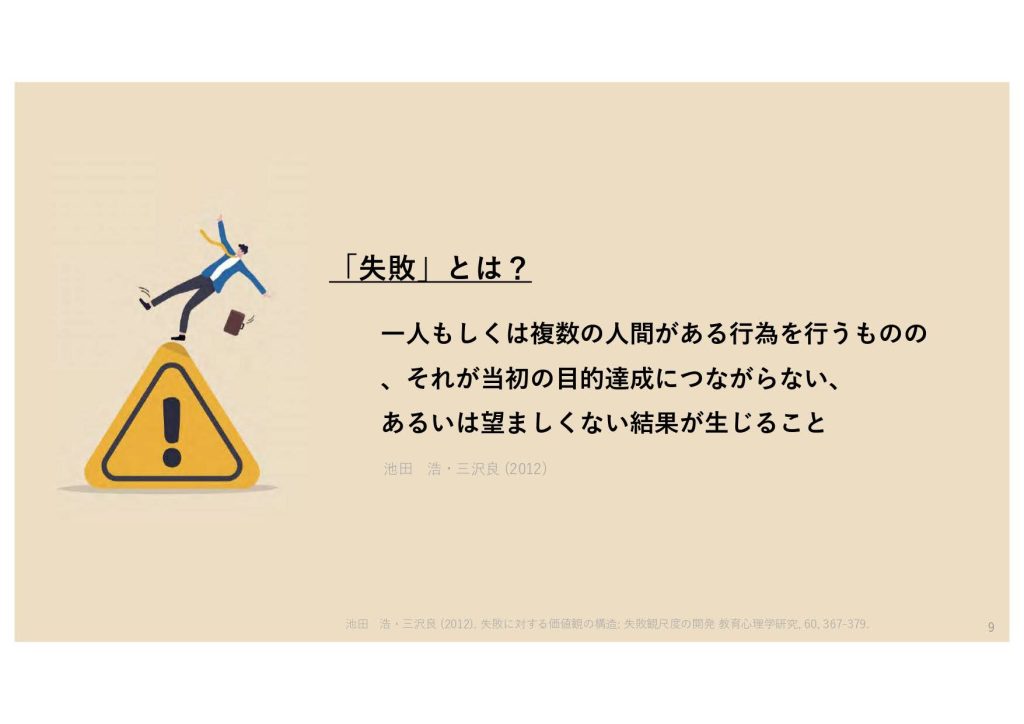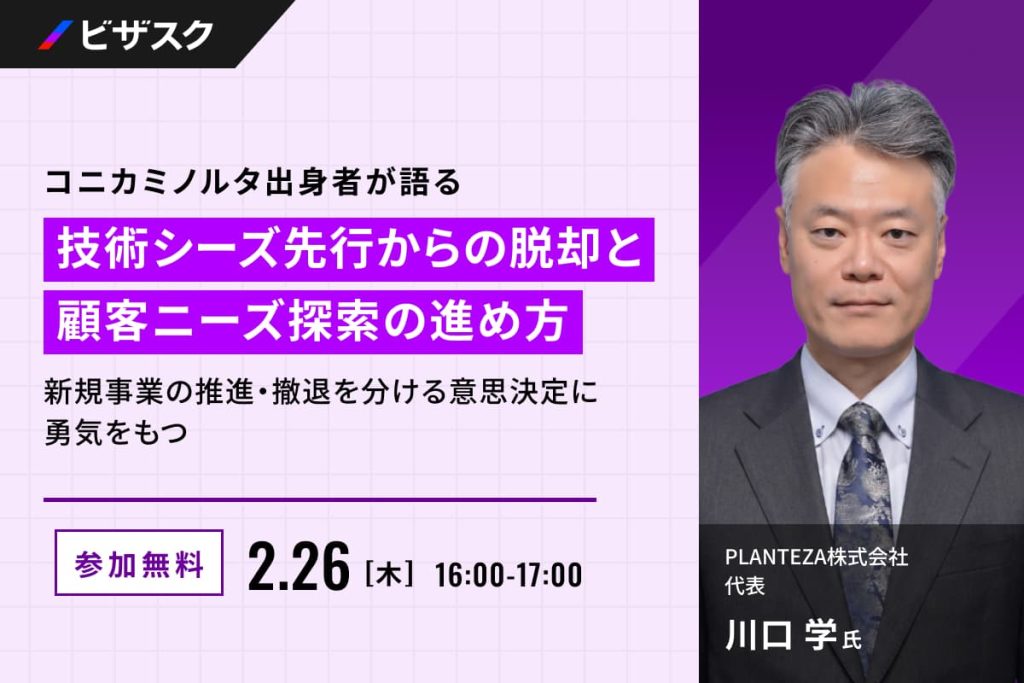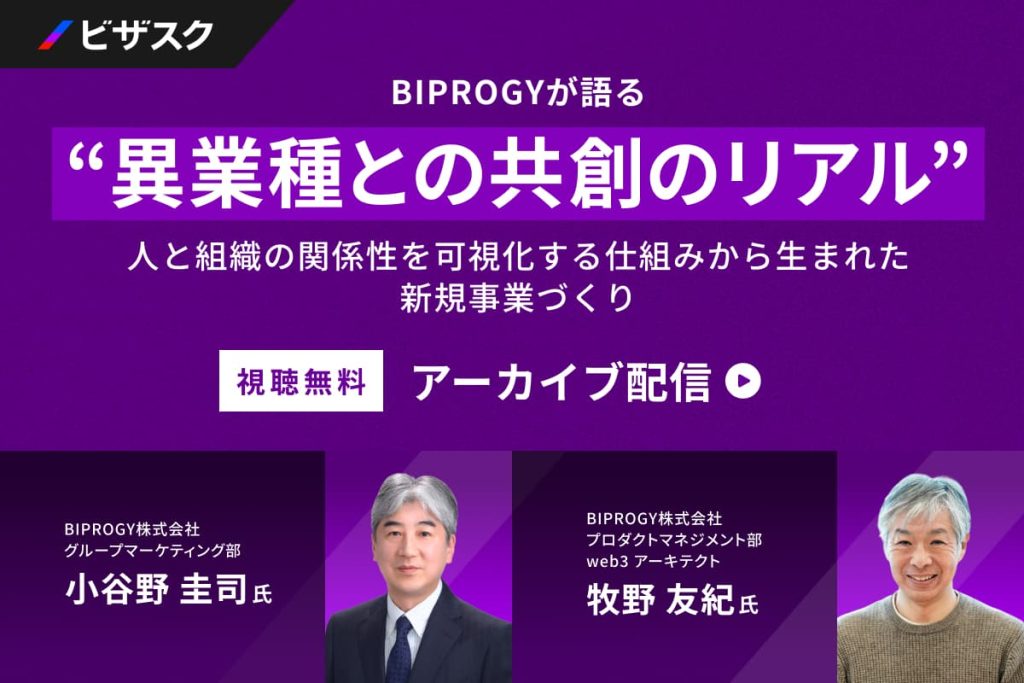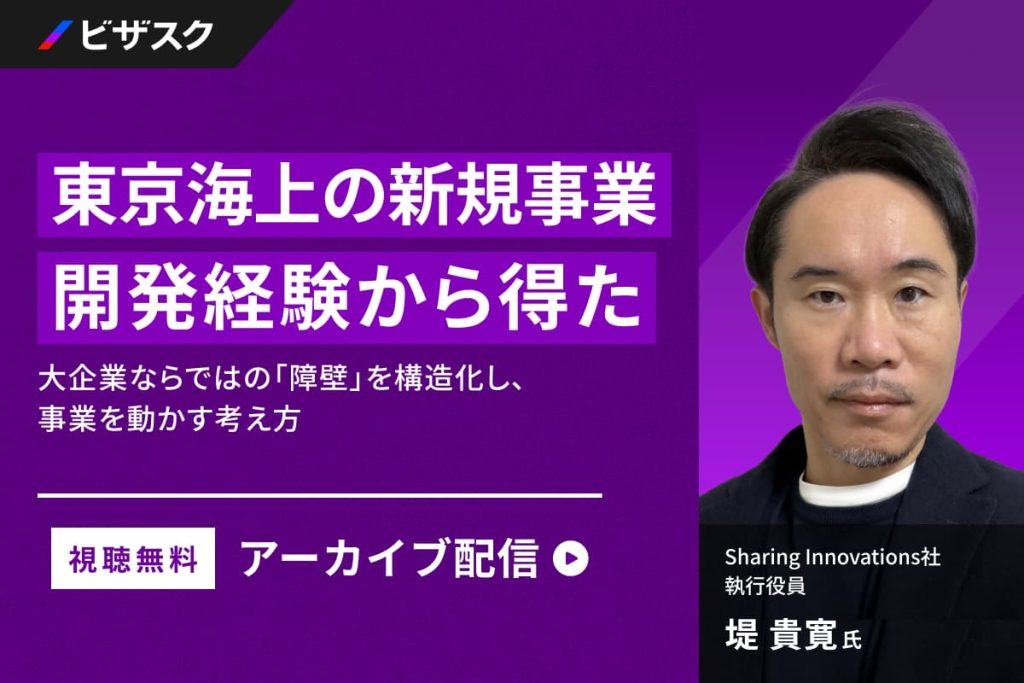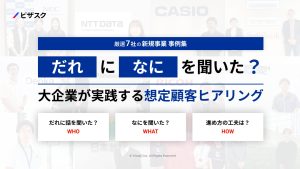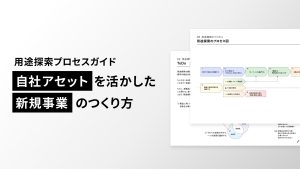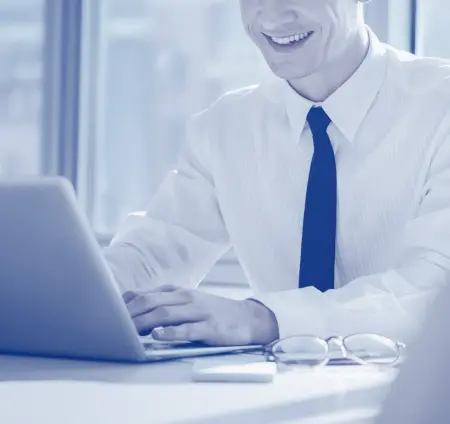有識者セミナーレポート
挑戦から学ぶ、 仮説検証の実践アプローチ
〜新規事業を前進させるために〜
新規事業を成功に導くためには、意図的に「失敗」し、そこから得られる学びを最⼤化することが不可⽋です。そのための強⼒な⼿法が「プロトタイピング」です。しかし、多くの現場では「何から⼿をつければいいのかわからない」「プロトタイピングの認識がチームでずれている」といった課題が聞かれます。
本レポートでは、プロトタイピングの専⾨家であるS&D Prototyping株式会社の三富 敬太⽒をお迎えし、新規事業開発における仮説検証の実践的アプローチについてご講演いただいたセミナーの模様をお届けします。プロトタイピングの基本的な考え⽅から、具体的な戦略、成功事例、そして組織に根付かせるためのカルチャー作りまで、新規事業を前進させるための知⾒を、登壇者の語りを追体験する形でお伝えします。
本レポートは、2025年6⽉19⽇に開催されたセミナーをレポート化したものであり、当該時点での情報に基づき作成されております。
登壇者プロフィール
三冨 敬太 ⽒
S&D Prototyping株式会社 代表取締役
「失敗から学ぶ技術
新規事業開発を成功に導くプロトタイピングの教科書」著者
プロトタイピング専⾨会社 S&D Prototyping株式会社 代表取締役。プロトタイピングについて学術的かつ実践的なアプローチを重視している。アカデミアでの活動はヒューマンインターフェース学会 ユーザエクスペリエンス及びサービスデザイン専⾨研究委員会 専⾨委員など。
著書:失敗から学ぶ技術 新規事業開発を成功に導くプロトタイピングの教科書
プロトタイピングについて
本章では、仮説検証の中核をなすプロトタイピングの基本的な概念について解説します。まず、プロトタイピングと密接に関わる「失敗」の本質を理解し、その上でプロトタイピングが何であるか、そしてその多様な定義や歴史的背景から⽣じる認識のズレを解消するための2つの視点について掘り下げていきます。
失敗とプロトタイピング
そもそも「失敗」とは何でしょうか。これは、ある行為が当初の目的達成につながらなかったり、望ましくない結果が生じたりすることです。私たちは、できるだけ失敗をしたくないと感じます。これは、心理学者のフロイトが提唱した「快楽原則」にもあるように、失敗によってストレスがかかり、ネガティブな感情が伴うため、本能的に避けようとする自然な反応です。
そして、そのストレスの⼤きさは失敗の⼤きさ、つまりかけた時間や⼯数に⽐例します。1年間準備したプロジェクトが失敗するのと、電⾞を1本乗り過ごすのとでは、かかるストレスが全く異なります。失敗の捉え⽅には、「ネガティブな感情を引き起こすもの」という⾒⽅もあれば、「学習の機会を与えてくれるもの」という⾒⽅もあります。失敗が起きた際の対応も、消極的に逃げるパターンと、積極的に向き合うパターンに分かれます。
プロトタイピングは、この「失敗」を「学習の機会を与えてくれるもの」として捉え、意識的に発⽣させるアプローチです。そして、その失敗に積極的に向き合うことで、学習効果を最⼤化する⽅法論、それがプロトタイピングなのです。
プロトタイピングとは
では、具体的なプロトタイピングの例にはどのようなものがあるのでしょうか。例えば、ソフトウェア業界でよく使われる「ワイヤーフレーム」は、画⾯の遷移などを確認するための代表的なプロトタイプです。
他に有名なものでいうと、デザイン会社IDEOが外科⼿術⽤の器具を開発した際のプロトタイプがあります。 当時、両⼿で⼿術をするのが当たり前だった状況で、「⽚⼿で操作できないか」というアイデアが出ました。その場でデザイナーがホワイトボードのペン、フィルムケース、洗濯バサミを組み合わせて「このような形で持てば⼿術ができるのではないか」と形にしたのです。 これも優れたプロトタイプの⼀例です。
また、ゲームセンターにある「ワニワニパニック」の最 初のプロトタイプは、段ボールとスリッパで作られていました。段ボールに⽳を開け、裏側からワニに⾒⽴てたスリッパを出し⼊れし、それを叩くことで「楽しいかどうか」という本質的な価値を検証したのです。このように、最終製品でなくても体験の本質が確認できれば、それは良いプロトタイプと⾔えます。
さらに、「エクスペリエンスプロトタイピング」という例もあります。新幹線の乗⾞体験を改善するプロジェクトで、俳優にお客さん役を演じてもらい、「お腹が空いているので⾷べ物を探す」といった指⽰書を渡して⾏動を観察したのです。これにより、乗客がどのような点で困るのかを学び、改善に繋げました。この事例では、俳優や指⽰書、そしてその環境⾃体がプロトタイプとなります。
ここで、「プロトタイプ」と「プロトタイピング」という2つの⾔葉を整理しておく必要があります。「プロトタイプ」は完成する前のモノや体験そのものを指し、「プロトタイピング」はそれらプロトタイプを活⽤した仮説検証のプロセスや⼿法を指します。
プロトタイピングの定義は⾮常に多く存在し、「アイデアの実験モデル」や「アイデアを形にしてユーザーに伝えること」など、様々です。このように定義が多岐にわたる背景には、歴史的な経緯が関係しています。プロトタイピンは1970年代に航空機などのハードウェアエンジニアリング分野で始まり、その後ソフトウェア分野、そしてデザイン分野へと広がっていきました。 そのため、分野ごとに定義が⼊り乱れ、分かりにくくなっているのです。
・・・(続く)
続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。