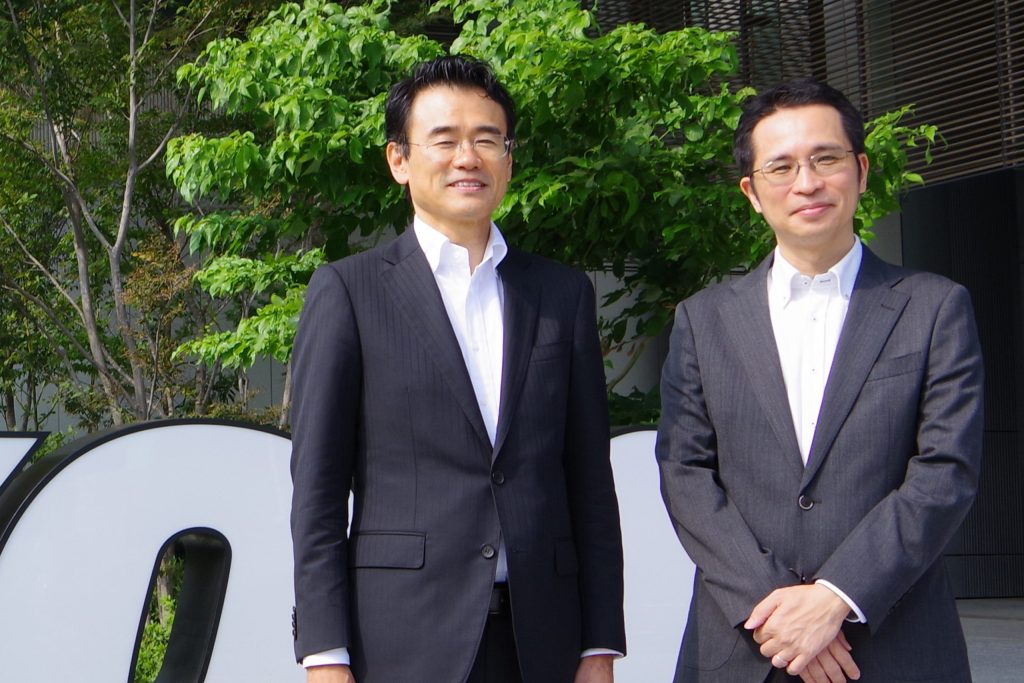活用事例
「やらない確信」を持てる強さーデンカが実現した市場起点の事業判断ー
概要
- エキスパート:素材メーカー社内のコネクションでは辿り着けない最終的な顧客層
- 依頼内容:ビザスクinterview、ビザスクnowを活用した販売妥当性の仮説検証
- 実施施策:専門家のアドバイスを元に仮説の方向性を修正、判断に掛かる時間を圧縮
所属されている部署のミッション
デンカ株式会社は工業用原料(無機・有機系)から土木・建築用材料、電子材料、食品包装材料、医薬品に至る、幅広い領域で事業を行う総合化学メーカーです。今回は、新事業開発部門 新事業創出部(以下、新事業創出部)に所属し、それぞれ異なるアプローチで新規事業創出に取り組む金親(かねおや)様と西京様のお二人に、新規事業開発におけるビザスクの具体的な活用法についてお話を伺いました。

原料を扱うメーカーの悩みは最終的な顧客へのアクセス
Q.お二人は新事業創出部の中でもご担当領域が異なると伺いました。詳細についてお教えいただけますか?
金親様:
私は新事業創出部の中でも、当社が注力する3つの領域「ICT & Energy」、「Healthcare」、「Sustainable Living」のうち、主に「Healthcare」領域を担当しています。ヘルスケアを軸にコラボレーションできる新たな領域や要素を探し出し、掛け合わせ、新たなビジネスを創出していくことをミッションとしています。
西京様:
私は「ICT & Energy」の領域を主に担当しています。特徴としては、当社がすでに持っているICTやエネルギーに関する技術や資源のさらなる活用方法を見つけ出し、新たなビジネスとすることが挙げられます。
Q. お二人それぞれ新規事業開発において、どのような課題がありましたか?
金親様:
私たちは素材メーカーという特性上、最終的な顧客へのアクセスが難しいという共通の課題があります。新製品の開発や新市場への展開を検討する場合、社内に知見を持つ人がいないため、誰に何を聞けばいいのかさえ分からない場合があります。そんな時、すでにビザスクを活用していた同僚から「ビザスクという専門的な人材に直接インタビューできるサービスがある」と紹介され活用しました。
求めている領域の専門家に数時間で辿り着けるスピード感
Q. 課題解決のために、ビザスクをどのように活用しましたか?
金親様:
私たちはそれぞれのプロジェクトの特性に合わせて、ビザスクのサービスを柔軟に使い分けています。例えば、私の担当するヘルスケア領域では、まず「ビザスクinterview」と「ビザスクlite」で数名の方にインタビューを行いました。そこで、検討していた仮説の妥当性を検証し、業界のトレンドや肌感などの基礎知識を得ることができました。
その後、より具体的な仮説を構築した上で、現在、オンラインアンケート「ビザスクexpert survey」を活用し、数十名規模のアンケート調査を行うため調整しています。自社内のリソースだけでこの人数の専門家にアクセスしようとしても数ヶ月かかるか、あるいは辿り着けないという結果になってしまう可能性もありますから、ビザスクを使用する価値があると思っています。
西京様:
「新規機能付与したセラミックを作る技術」という特定の技術シーズの用途を探るプロジェクトでは、少し異なる使い方をしました。まず24時間以内に回答を得られる「ビザスクnow」で、「この技術はどこに使えそうか」というアイデアを広く募集しました。その回答から有望そうなレンズ用途に狙いを定め、次に1時間単位のインタビュー「ビザスクinterview」でより深い知見を持つ専門家へヒアリングを行い、事業化の可能性を深掘りしていきました。
顧客は本当にこれを求めているのか?
Q. ビザスクを活用したことで、どのような成果がありましたか?
西京様:
最大の成果は、本格的な開発に着手する前の段階で、事業の方向性を迅速に、かつ的確に判断できるようになったことです。先ほどのセラミックスの事例では、専門家へのヒアリングを通じて、想定していたレンズ用途では技術的な難易度が非常に高く、事業化は困難だという結論に早期に至りました。
もしビザスクを使わずに開発を進めていたら、多くの時間とコストをかけた後に「やはり使えなかった」という結果になっていたかもしれません。こうした開発の手戻りを未然に防げるのは、非常に大きな価値だと感じています。また、外部の専門家から得た一次情報を社内で共有することで、「お客様は本当にこれを求めているのか」というマーケット視点での議論が活発になりました。部署内での情報交換も促進され、組織全体に顧客視点の文化を醸成する一助になっていると感じます。

AIの「答え合わせ」は専門家
Q. 最後に、今後の展望についてお聞かせください。
金親様:
世の中のトレンドである生成AIを弊社も積極的に活用しています。まず生成AIで広く情報を集め、基本的な質問項目を作成し、その上でビザスクのインタビューに臨むことで、限られた時間の中でより深く、本質的な議論ができています。生成AIが提示する情報は網羅的ですが、専門外のジャンルでは、情報の重要性や鮮度を、自力で判断することができません。実際に生成AIで調べた内容をインタビューで専門家に聞いたら事実と違った、というようなこともありました。「答え合わせ」や「情報の検証」のために専門家の知見を活用するという使い分けが、非常に有効だと感じています。
西京様:
専門家を探せるサービスは他にもありますが、ビザスクは登録者数が多く、求める知見とマッチしやすいです。さらに、知見の活用方法にバリエーションがある点も魅力で、今後も活用したいと思います。次のステップとしては、ある程度開発が進んだ製品の新たな用途を探索するために「ビザスクweb展示会」の活用も検討しています。自分たちでは思いもよらないような使い方やアイデアに触れることで、事業の可能性をさらに広げていきたいです。これからも様々なサービスを活用し、マーケットインの発想で新規事業を創出していきたいと考えています。
利用したサービス
※リニューアルのお知らせ
2025年9月1日よりビザスクliteは【ビザスクdirect】にリニューアルしました。
ビザスクdirectではインタビューに限らず、採用や業務委託にもご利用いただけます。
※リニューアル後の【ビザスクdirect】は、
旧サービスビザスクliteとは一部仕様・料金が異なります。